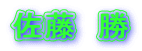 さんのコーナー |
 |
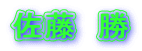 さんのコーナー |
 |
|
花見川春秋(3) ─大願成就? 古希直前のフル完走!(2)─ |
|
花見川春秋(3) ─大願成就? 古希直前のフル完走!(1)─  当日は出来るだけ余裕をもって会場に到着しようと早朝6時に千葉の家を車でスタートした。何度もカーナビで会場を検索して片道の距離は約100キロで2時間のドライブを見込んでいた。首都高速から東北道を経由して加須インターで一般道に下り、約30分ほどでメーン会場のある古河市役所の中央運動公園陸上競技場に到着した。渋滞や迷うことなく殆ど予定どおうりの行程であった。 当日は出来るだけ余裕をもって会場に到着しようと早朝6時に千葉の家を車でスタートした。何度もカーナビで会場を検索して片道の距離は約100キロで2時間のドライブを見込んでいた。首都高速から東北道を経由して加須インターで一般道に下り、約30分ほどでメーン会場のある古河市役所の中央運動公園陸上競技場に到着した。渋滞や迷うことなく殆ど予定どおうりの行程であった。フルマラソンスタートにはまだ2時間もの時間があるせいか競技場のあちこちでたくさんのランナーが軽く走ったりストレッチなどをしている。いつものことながら会場でこのような光景を見ると自然とあせりが出てきてしまう。自分の準備は完璧なんだろうか? 途中で足を引きずるようなことにはならないだろうか? などなどの気がかりである。 スタート25分前になるとグランドに放送で参加選手の招集が知らされた。あちこちに散らばっていた選手がまるで牧場の牛の群れが一か所に集まるが如くにスタートラインの方向に動いた。  10時丁度に“ぱーん”と乾いたピストルの音が遠くの方に聞こえて、徐々に群衆が動き出した。マラソンレースの一番の興奮のひと時である。まるで人間の行列というよりも大きな川の流れに例えた方がよさそうな光景そのものである。それもみな男女それぞれ思い思いのカラフルなトレーニングウエア―を着ているので綺麗な華やかな流れでもある。大地に7,000人の足音だけが軽快に鳴り響いている。“焦るな、距離は長いんだ! ゆっくり行かなければ途中でばてるぞ!……”と私はひたすら自分にいい聞かせて黙々と走った。 10時丁度に“ぱーん”と乾いたピストルの音が遠くの方に聞こえて、徐々に群衆が動き出した。マラソンレースの一番の興奮のひと時である。まるで人間の行列というよりも大きな川の流れに例えた方がよさそうな光景そのものである。それもみな男女それぞれ思い思いのカラフルなトレーニングウエア―を着ているので綺麗な華やかな流れでもある。大地に7,000人の足音だけが軽快に鳴り響いている。“焦るな、距離は長いんだ! ゆっくり行かなければ途中でばてるぞ!……”と私はひたすら自分にいい聞かせて黙々と走った。コースは市内の目抜き通りを駆けたり郊外に出たりするほとんどフラットなコースであった。今回この町でのマラソン大会は初めての開催であり、市からの宣伝が行き届いているのか沿道にはたくさんの応援の方々が小旗を振り振り、声援を惜しみなく下さっていた。 |
花見川春秋(2) ― 孫の顔見たさに850キロ − |
花見川春秋(1) 第7回東京マラソンも目の前に迫った(2月24日)。センセーショナルにスタートしたこの大会も回を重ねてもう今年で7回目(7年目)になろうとしている。 |
|
5年目の病院ボランテア(出来ることの幸せ) 毎週、月曜日と金曜日の朝8時頃に私は黄色と緑とブルーの模様が描かれているエプロン(写真)を付けて千葉大学附属病院の総合受付に立つ。 受付で来院された患者さんやそのご家族が迷わないように案内役を務めるボランテアの仕事である。 |
| =思い出の品= 誰にでも“思い出の品”というものがあるものである。今回の東日本大震災の被災地でも多くの被災者が破壊された我が家の瓦礫の中を失望に打ちひしがれながらそれを探している姿が何度も涙を誘った。  私には二つの思い出の品がある。それも両方ともガラス製品である。ひとつは「ワイングラス」でありもうひとつはビール用の「マグカップ」である。 私には二つの思い出の品がある。それも両方ともガラス製品である。ひとつは「ワイングラス」でありもうひとつはビール用の「マグカップ」である。ワイングラスは私と家族が5年前に北海道に旅行した折、小樽の市街地にある有名な北一ガラスで購入したものである。初冬の川の水面に張った非常に薄い氷のような製品で強く握るとパリンと割れそうな感じの物であった。ガラスの表面にはワイングラスらしく綺麗な一対のブドウの模様が描かれている。旅行した時に私の妻の身体には既に肺がんが発見され闘病中であった。このグラスを購入する時には私は自分なりにあるゲンを担いでそれを眺め、手に取りレジに向かった。この直ぐにでも割れそうなグラスは私が家に帰っても「ずーとKeepして使いうことが妻の病状にも関係する」という変な自分なりの理屈付けであった。 もうひとつのビールのマグカップは定年後に大学のいつもの海外旅行メンバー(4人で毎年必ず南国のリゾートエリアに出かけていた)で南太平洋のタヒチ島に旅行した時購入した物である。現地で3日間ほど滞在したのであるが、そのツアーのなかに現地のビール工場を視察するイベントがあった。現地の地ビール  の銘柄は「Hinano」というブランドで、トレードマークは横向きに坐った小麦色した肌の若い女性があしらわており、その黒い長い髪に真っ赤なハイビスカスの髪飾りが特徴的である。友人のK君とMY Cupで帰国してからもこれで時々ビールでも飲もうや・・・とお揃いで買い求めたものである。 の銘柄は「Hinano」というブランドで、トレードマークは横向きに坐った小麦色した肌の若い女性があしらわており、その黒い長い髪に真っ赤なハイビスカスの髪飾りが特徴的である。友人のK君とMY Cupで帰国してからもこれで時々ビールでも飲もうや・・・とお揃いで買い求めたものである。ふたつのCupは今でも私の家のカップボードに並んでいる。しかし、私の妻は北海道の楽しかった旅行を思い出に、その翌年の秋にはついに帰らぬ人となってしまった。その時のワイングラスは今でも傷ひとつなく綺麗な姿のまま、時として私の晩酌のテーブルの上で輝きを放っている。 またK君も一昨年に長年の肝臓の病から逃れらることなく遠い旅路に出てしまった。この二つのガラス製品は毎日私の目にとまり、そしてその時に妻の笑顔がそこに映り、そして親友K君のはにかんだような笑顔が浮かぶのである。妻との北海道の旅行、そして親友とのタヒチ旅行の忘れられない思い出の品々としてこの二つはこれからもワインを飲む時、はたまた気分転換でビールを飲む時、折に触れていろいろと私に語りかけてくれることを願っている。 |
| =国立劇場にて初めての歌舞伎鑑賞= 7月中旬に国立劇場(半蔵門)に行き歌舞伎を鑑賞してきました。私にとりまして歌舞伎は生まれて初めての経験であり演目は「身替座禅」というものでした。 今まで何度か歌舞伎を見る機会はあったのですがどうしても自分には難しい(特にセリフ)と思い敬遠して実現しませんでした。 しかし今回は国立劇場が実施している「歌舞伎鑑賞教室」の一環として開演されており解りやすいのでは  ないか……と思い足を運びました。実際にこの演目はストリー的にも単純でコメデー基調で私のような素人にも楽しめるものでした。 ないか……と思い足を運びました。実際にこの演目はストリー的にも単純でコメデー基調で私のような素人にも楽しめるものでした。それに加えて鑑賞教室ということもあり本命の演目が始まる前と終演の後に若手歌舞伎役者、中村壱太郎、中村隼人の二人による歌舞伎全般の解りやすい解説がありました。歌舞伎人気が低迷なのかどうか分らないが歌舞伎人気底上げの為の二人の熱意が一挙手一投足から感じられた。 もともと前記のごとく60有余年生きてきても今回のような歌舞伎、浄瑠璃、狂言などなどの古典芸能にはほどほど縁が無かったが昨年千葉市民大学で受けた講座から少々興味を持ちだしたのである。 その講座は国立歴史民族博物館名誉教授の「桧史、豊臣の江戸時代史」(豊臣秀頼は生きていた─大阪夏の陣後の伝承をたどる)であった。 大阪夏の陣で豊臣方は敗れ徳川の天下になりそれから300有余年その安定した時代は続いたのであるが、その時代の潮流の中にあってなお徳川の天下をよしとしない大坂方(旧豊臣勢力側)が歌舞伎や浄瑠璃などを通して自分たちの意思表示をしていた。それを演じる側、それを楽しむ側はそれぞれ暗黙の意思統合があり、また時の為政者もそれを見て見ぬふりをして黙認していたらしい(ガス抜きの効果狙い?)。 今回の「身替座禅」はそのようなドロドロしたものではないが、やはり人間の心の中に潜む浮気心、嫉妬、怒り、絶対服従の上下関係などがコミカルなテンポの中で演じられており、可笑しいやら悲しいやらで退屈するどころではなかった。 説明によるとこの演目は海外でも数多く公演されて、言葉の異なるアメリカや韓国でさえも爆笑を呼んだ人気番組とのことである。是非一度劇場に足を運ばれることを勧めてやみません。 |
|
=秘境“秋山郷”訪をねて= 秋山郷は、長野県の最北端にあり、その県境は新潟県そして群馬県の2県にまたがる栄村の一部をなし山深い温泉郷である。冬には積雪量がかっては日本一の7m85cmを記録したことがあると言うからそれだけでもいかにそこが秘境であるかが窺われる。千曲川に合流する中津川の源流もその秋山郷の近くの佐武流山の中腹にあり、郷はその中津川の急流に沿って存在している。 |
| =マラッカ海峡クルージング (シンガポール、ペナン、プーケット6日間)= 2月28日より3月5日までの6日間、スーパースターバーゴ(SuperStar Virgo=乙女座 76,800トン)という客船で娘達と「つかの間」のクルージングを楽しんできました。  成田からシンガポールまでの往復はJALのフライトでしたがシンガポールから先のマラッカ海峡沿いの移動はすべて上記の船での移動でした。都内の某旅行会社が昨年の10月ごろに新聞で大々的(一面広告)に宣伝広告をしているのを見てそのツアーに応募しました。何回かの出発日があったのですが我々のスタート日が一番多くの参加者があったとかで、東京、大阪合わせて約200人の参加者がありました。 初日は成田空港を午後便にて出発し、深夜にシンガポールのホテルに入り、翌日の市内観光に備えて早々に休みました。翌日からの生活はすべて船の中の自分達の船室が「自宅代わり」となり以後5日間の生活の拠点となりました。 シンガポールでの市内観光はいつもとあまり変わり映えのしない「マーライオン」や「スタンフォードラッフルズ立像」であり「オーチャードロード」でありましたが、初訪問の娘達は美しい街並みにいささか興奮気味で、盛んにカメラに周りの光  景を収めておりました。夕方近くに港に向かい初めてそこに停泊していた客船「スーパースターバーゴ」を見た時にはやはりその大きさに圧巻を覚えました。日本国内最大級の豪華客船「飛鳥II(49,000トン)」をはるかに越える大きさで全長268メートル、全幅32メートル、乗客定員約2,000人はまさしく「洋上に浮かぶ街」と言う名にふさわしいものでした。乗船時にはゲートに税関がありましてパスポートを見せての出国手続きが必要でした。着岸した船に乗り込むための長い通路を進んでゆくと途中に船のスタッフらしき人々が趣向を凝らした様々な歓迎のパーホーマンスをしてくれていました。ギャラクシーという船首にある大きなそしてすばらしい見晴らしの楽しめるホールに日本から来た乗客は全部集められて、これから始まる5日間のクルージングにおける船内生活の案内がありました。 景を収めておりました。夕方近くに港に向かい初めてそこに停泊していた客船「スーパースターバーゴ」を見た時にはやはりその大きさに圧巻を覚えました。日本国内最大級の豪華客船「飛鳥II(49,000トン)」をはるかに越える大きさで全長268メートル、全幅32メートル、乗客定員約2,000人はまさしく「洋上に浮かぶ街」と言う名にふさわしいものでした。乗船時にはゲートに税関がありましてパスポートを見せての出国手続きが必要でした。着岸した船に乗り込むための長い通路を進んでゆくと途中に船のスタッフらしき人々が趣向を凝らした様々な歓迎のパーホーマンスをしてくれていました。ギャラクシーという船首にある大きなそしてすばらしい見晴らしの楽しめるホールに日本から来た乗客は全部集められて、これから始まる5日間のクルージングにおける船内生活の案内がありました。(1) 船室(自分たちだけの居住空間) 客室は全部で3種類ありそれぞれ設備のちがいがあって当然価格もそれぞれ違いました。最高のAクラスには個室の外の海側にバルコニーが付いていてキャビンでゆっくりクルーズを楽しむタイプ(Ocean View Sweet Room)でした。Bクラスはバルコニーは無く海側に窓ありで、Cクラスは外が見えないタイプになっておりました。勿論すべての船室にはトイレ、シャワー、冷蔵庫、デスク等が完備されており、毎朝その日の船内予定が案内された「船内新聞」が届けられました。ゲストはその新聞によりその日一日どこのフロアーで何があるとか、どこのレストランではこんな料理が食べられるとかを知ることが出来ました。広い船内なのでその情報がないとただうろうろするばかりだったと思います。 (2) 船内施設(洋上の都市)  船内には16ケ所のバーやレストランがあり世界各国の料理が楽しめるほか、本格的な音響、証明施設を備えた巨大シアターもあり、ラスベガスさながらのショーやコンサートが毎日開催されておりました。そのほか、スイミングプール、ライブラリー、スポーツジム、ギフトショップ、デスコ&ナイトクラブ、ビュテーサロン、ゲームセンターなどなどがあり、時間をつぶすにはまったく苦労しませんでした。最上階の屋外ブールにはジャクジー、サンデッキがあり、その周りでは毎日何らかのショウが行われていました。さんさんと太陽の光がふりそそぐプールサイドで冷たいビールを飲みながらのんびりと「至福のひと時」を過ごせたのは言うまでもありません。加えて嬉しかったのは船内を一回りするジョギングコースが設けてあり、毎日食欲増進のために走ることが出来たことでした。早朝の6時ごろまだ朝の太陽が水平線から昇りくる前にひたすら走っている多くの外国人(ああそうか、自分も外国人なのだ?)を見かけました。船内のアトラクションで「ヨガ教室」があり娘たちと参加したのですが、自分の身体の硬さに驚愕し帰国してから週一度「ヨガ教室」に通うようになりました。 船内には16ケ所のバーやレストランがあり世界各国の料理が楽しめるほか、本格的な音響、証明施設を備えた巨大シアターもあり、ラスベガスさながらのショーやコンサートが毎日開催されておりました。そのほか、スイミングプール、ライブラリー、スポーツジム、ギフトショップ、デスコ&ナイトクラブ、ビュテーサロン、ゲームセンターなどなどがあり、時間をつぶすにはまったく苦労しませんでした。最上階の屋外ブールにはジャクジー、サンデッキがあり、その周りでは毎日何らかのショウが行われていました。さんさんと太陽の光がふりそそぐプールサイドで冷たいビールを飲みながらのんびりと「至福のひと時」を過ごせたのは言うまでもありません。加えて嬉しかったのは船内を一回りするジョギングコースが設けてあり、毎日食欲増進のために走ることが出来たことでした。早朝の6時ごろまだ朝の太陽が水平線から昇りくる前にひたすら走っている多くの外国人(ああそうか、自分も外国人なのだ?)を見かけました。船内のアトラクションで「ヨガ教室」があり娘たちと参加したのですが、自分の身体の硬さに驚愕し帰国してから週一度「ヨガ教室」に通うようになりました。(3) 食事(世界の料理を満喫)  食事は船内にある多数のレストランの中で無料(旅費の中に含まれている)の所とそうでない所(別会計)の2種類がありました。乗船のときにCredit Cardのようなものを個人個人が渡されてそれが船内いたる所で現金の代わりに使用され、最終日に精算というシステムになっていました。高級な日本料理店(寿司バーやステーキハウス)などは有料でしたので、我々はほとんど使用せずもっぱら無料のバイキング食堂を使用していました。種類もボリュウムも充分にありデザート、ドリンクも充分好みに合いました。 食事は船内にある多数のレストランの中で無料(旅費の中に含まれている)の所とそうでない所(別会計)の2種類がありました。乗船のときにCredit Cardのようなものを個人個人が渡されてそれが船内いたる所で現金の代わりに使用され、最終日に精算というシステムになっていました。高級な日本料理店(寿司バーやステーキハウス)などは有料でしたので、我々はほとんど使用せずもっぱら無料のバイキング食堂を使用していました。種類もボリュウムも充分にありデザート、ドリンクも充分好みに合いました。(4) キャプテンデナーパーテイ 船長が乗客をデナーに招待するイヴェントでこの時だけはセミフォーマルな服装で夕食に招待されました。しかしそれほど堅苦しいものではなく、船長や他のクルーメンバーが制服に身を包み、我々と親しく話したり写真におさまったりして和気藹々のものでした。若い男女のスタッフが入れ替わり様々な国のファッションショーをメインステージで見せてくれました。日本から参加された女性の和服姿もちらほらいました。 (5) 寄港地での観光  客船は途中2箇所に立ち寄りそれぞれの観光名所を訪ねるコースがOptionとしてありました。しかし、いずれの寄港地の海岸も底が浅く船が着岸出来ないのでタグボートに数十名づつ分乗して上陸しました。ボートに移り船底から岸壁のような船を見上げた時、そして砂浜にたどり着いて遠く沖合いに浮かぶ白い客船を見た時、改めてその大きさに驚いたものでした。最初の寄港地はマレー半島のペナン島した。「南海の楽園」といわれマレーシアを代表するビーチリゾート地だけあってまた18世紀後半から東インド会社の貿易港として発達してきた町だけに異国情緒があふれていました。30度を越す暑い中、有名な「トライショー(人力車)」に乗り市内を観光しました。2度目の寄港地はタイのプーケット島でした。バンコックの西南の洋上に浮かぶタイ最大の島でその美しさから「アンダマン海の真珠」と賞賛されて世界中から観光客が集まるそうである。ビーチでは沢山の海水浴客がカラフルなパラソルの下で思い思いのくつろいだ時間を過ごしていました。砂は細かく白く足ざわりがとても気持ちの良いビーチでした。出来ることならここにのんびり一月くらい滞在したいものだと思いました。 客船は途中2箇所に立ち寄りそれぞれの観光名所を訪ねるコースがOptionとしてありました。しかし、いずれの寄港地の海岸も底が浅く船が着岸出来ないのでタグボートに数十名づつ分乗して上陸しました。ボートに移り船底から岸壁のような船を見上げた時、そして砂浜にたどり着いて遠く沖合いに浮かぶ白い客船を見た時、改めてその大きさに驚いたものでした。最初の寄港地はマレー半島のペナン島した。「南海の楽園」といわれマレーシアを代表するビーチリゾート地だけあってまた18世紀後半から東インド会社の貿易港として発達してきた町だけに異国情緒があふれていました。30度を越す暑い中、有名な「トライショー(人力車)」に乗り市内を観光しました。2度目の寄港地はタイのプーケット島でした。バンコックの西南の洋上に浮かぶタイ最大の島でその美しさから「アンダマン海の真珠」と賞賛されて世界中から観光客が集まるそうである。ビーチでは沢山の海水浴客がカラフルなパラソルの下で思い思いのくつろいだ時間を過ごしていました。砂は細かく白く足ざわりがとても気持ちの良いビーチでした。出来ることならここにのんびり一月くらい滞在したいものだと思いました。(6) 終わりに 今回、このクルージンを体験して思うことは、今まで庶民には手が届かない「高嶺の花」と思いがちだった豪華客船の「クルージング」も決してそうではないということである。それは確かに100日以上もかける世界一周の船旅もあり費用も数百万円するものもあると思うが、私から見ると逆にそんな長期のものは退屈で耐えられないと思う。また今回のように観光地を織り込んだクルージングの場合通常の観光旅行と違い、重い荷物を持ちあちこち移動する必要が無いので本当に楽で、旅が気軽に思え楽しさも倍増である。旅を終えた今でもあの船上から眺めたマラッカ海峡の水平線に沈む茜色の夕日の美しさを鮮明に思い出すことが出来る。 |
|
=東大公開講座 ”バランス” に参加して= |
|
=バイクでお遍路?四国一周1,400キロの旅= 1.やはり四国でした……あちこちで”お遍路さん”の姿を見受けました。殆どの方が白装束に笠を被り杖をついていました。笠には”同行二人”と書かれてました。苦しい修行の旅は常に一人でなく日蓮さん?(あるいは先立たれた大切な人?)との同行しているとも意味らしいのですが……真夏の炎天下でも冬の手足がガかじかむような寒さの中での己の足を使ってこその巡業こそ意味があると思うのですが、最近ではバスやマイカーでさっと廻ってしまう人や、中には”代行屋”がいてその者に札所を回ってもらい”ご朱印”を集めている人も居るとか?
|
|
=初秋の北海道、東北を駆ける= ちょっと北海道の観光ピークが過ぎた頃だろうと見込んで北海道(道南)と、帰途は函館から青森県の先端大間に抜けて東北を南下する単独ツーリングに行ってきました。 |
|
へそ出し、角出し、菊ねり ? へそ出し、角出し、菊ねり、といきなり言われての何のことかチンプンカンプンのことと思います。これは“そば打ち”の時のそば粉の練り方の名前です。 |
|
四万温泉旅行 |
|
ピッカピカの一年生(また大学へ?) この度、還暦を過ぎて再度大学に入学いたしました…と言いますと大方の方が 「えっ?」と驚かれるでしょう。それもそのはずこの大学は地元千葉県が企画、運営しております「千葉ふるさと文化大学」(2年制)なのであります。
今期募集は8期生(毎年募集=8年目)で入学者数は合計105名の人数で、その新入生は千葉市を始め船橋市、浦安市、松戸市など千葉県全土に渡っております。
建学の主旨は主にシニア世代の方たちにこれからの人生に生きがいと充足感を持って歩んでいただこうとの目的で8年前に発足したものであり、テーマは「房総の地域に根ざす歴史などの伝承文化の再発見」を中心とした講座と受講生の二ーズに応じた多様なクラブ活動と探訪ツアーの展開であります。既に4月14日に一年先輩に当たる7期生と県教育会館にて合同入学式がとりおこなわれ、そのときは校歌まで披露されました。
大ホールには200人以上のシニアクラスの男女が参集し、それはそれは強力なパワーを感じました。還暦を過ぎてもまだまだ学びたいと希望する先輩達がこんなにもおられるのだと感銘するとともに、自己の胸の中にも勤勉意欲がわいてきました。式が終わりましたあとの廊下にはまるで通常の大学と変わらないように各サークルのテーブルが出来ておりまして、新会員の募集を受け付けておりました。
5月12日には第1回目の講義が行われ、「郷土の偉人群像」というテーマで、講師から千葉の偉人「伊能忠敬」と「大原幽学」のお二人の話がありました。
千葉に居住するものの一人として千葉に関わる先人や歴史的建造物などの学習をこれから2年間かけて行うわけですが、学習を通して多くの方々と知り合いになれ、そして自分の古里ではないにしても自分達の子供が生まれたこの千葉のことをよりよく理解できる二つの大きなメリットがありますので、何とか継続して卒業免状を頂きたいと今から張り切っています。
サークル(同好会)も「歴史・民族探訪クラブ」、「美術館散歩クラブ」、「里山クラブ」、「写真・街角ウオッチング」、「陶芸クラブ」などなどたくさんありますが、私は「そばグルメ倶楽部」に入会することに決めました。いつか家族に美味しいそばをご馳走してあげたいものです。
最後に初日の講義(上記)で習いました両偉人の共通の実践したことを記して終わりにします。
「学ぶことは生きること!生きることは学ぶこと」
|
|
ボランテア活動1年が過ぎて──特定非営利活動法人”ワールド・ビジョン”── 3月11、12日の朝、私が参加しておりますNGOの組織「ワールド・ビジョン(World Vison Japan)」がテレビ放映(タイトル=ライフライン<30分番組>)されたために多くの43会の仲間や以前の会社の友人などから「見たよ!」と連絡を戴きました。私が定年退社後このような活動に関係していることを知らなかったという内容とこの組織の活動内容についての質問が多々ありましたので、簡単にお話したいと思います。
ワールド・ビジョン(以後WV)は1950年に設立された世界約100ヵ国で緊急援助から自立支援まで一貫した支援活動をおこなっている国際NGOでして、チャイルドスポンサーシップというプログラムのもとに世界約220万人の子供達を支援しています。
調査によりますと親をエイズで失った子供は世界で1,500万人、開発途上国に住む栄養不良の子供は約1億5,000万人、また家族を支える為に働かなければならない子供は世界で約2億5,000万人にも及びます。上記のチャイルドスポンサーシップはこうした子供達が支えられる為にスポンサーと言われる方に月々4,500円を継続的に支援いただき、地域の貧困を解決するプログラムです。
WVが紹介する支援チャイルドとの文通や毎年お送りする報告書を通して「支援の成果」を実感できるのが大きな特徴です。
この現地の支援チャイルドと日本国内のスポンサー(支援者)を結ぶWVJ(World Vision Japan)の仕事をお手伝いしているのが我々ボランテアの仕事になります。
仕事の内容は報告書、手紙等の区分け、封入、発送、案内などの印刷、手紙(現地←→日本)の翻訳など多岐にわたります。仕事の内容はシンプル作業が多いのですが、これらの仕事も外注に出した場合かなりのコストUPになりますので、支援者の貴重な浄財を少しで多く子供達に還元する為にはとても大事な仕事になっています。
現在ボランテアの登録数は約200人になり、その方々の内容は正に様々です。お子様が大きく成長なされ手が掛からなくなったお母さん、定年退職して時間の余裕が出来たお父さん、大学、大学院在籍の学生さん(授業のない日)、将来WVのような海外援助の仕事につきたい若者、海外留学生など様々です。
週に2、3度参加、週1の参加、隔週の参加、月1の参加など出勤(?)日数は個人の生活パターンにより自由です。
毎日だいたい10人から15人くらいの参加者ですが皆黙々と作業をしております。手を動かしながら、あるいは翻訳のPCの画面を見つめながら、皆さんの頭の中には遠い地球の裏側の国々、アフリカや南米の地で貧困に耐えながらも明日に向かっていきいきと目輝かせている子供達の顔が浮かんでいるように感じます。
ランチの時間や3時の休憩の時などはひとつのテーブルを丸く囲み最近の出来事、昔あったこと、スポーツの事、生活の知恵?など老若男女が混在して楽しいそして「生き字引団欒の場」になります。
ボランテアに関して人様々な意見がありますが、私の考えはいろいろ批評をすることよりも先ず自分で行動に移しそこから考えようとスタートしました。定年退職まで大病も大きな事故、災難もなく生きて来れましたのは何かの力でそうさせてもらったのであり、今後は少しでもその恵まれた部分を社会の底辺の方々に還元出来ないかと思案していた時にWVJのスローガン=”何もかも”はできなくても、”何か”はきっとできる=が目に飛び込んできました。
この活動を通じて多くの現実を知りそして多くの善良な人々(ボランテア仲間)を知りえたことは私にとりまして「賃金に勝る大きな報酬」ではなかったかと思っております。
|
|
人生の中の原点 最近思うことがあります。
還暦を迎え人生の「最終章」に移り行く自分を出来るだけ客観的に観た時に、あることに気が付きました。
「人間には誰しも一つの原点がある」と思えてならないのです。母の子宮から生まれ幼児期、児童期、少年期、と成長してゆく過程の中で、あるひとつのことにぶつかる──それは一時的なもの、あるいはある程度時間経過のあったもの、あるいは一地点的のもの、あるいはある程度地域性のあるもの──いろいろである。
そのことがその時点ではさほど意識しなのであるが何時しか頭脳のある部分に沈殿している。それは癌細胞でもなんでもなく普段はなにもしないでおとなしい。しかし、その後の人生の中で大きなトラブルや苦境にはまると無意識のうちにその奥深い細胞のようなものを探り当てに行く。
その奥深い細胞はまさに座標軸の「原点」であるかのようで、どのように進んだ双曲線も放物線も全てのベクトルはまた最初の原点「ゼロポイント」に帰って来る。その原点でまた新たなエネルギーをもらって再度X軸とY軸に囲まれた座標の空間に羽ばたいてゆく。
私の原点は小学校の低学年にあった。5年の時に他の小学校に転校になったので2〜3年生の頃だったかもしれない。
昭和24、5年頃私は長野県の信州中野という所に母と兄姉4人で住んでいた(父は既に死去していて他の2人の姉は東京に出ていた)。
終戦直後でとにかく生活は貧しかった。食べるものもろくになかった。東京で生まれたのだが、空襲を避けるために田舎の親戚を頼りに移り住んだ為に肩身の狭い思いの毎日であった。
小学校にはその頃もちろん給食も始まっておらず皆家から弁当を持参していた。 その頃の私の家で朝は何とか食べても弁当に詰めるご飯やおかずが無かった。いつも後から母がもって行くから・・・と持たせてもらえなかった。しかし毎日と言っていいほど昼の時間には間にあわなかった。教室で皆が「いただきます!」と大きな声で言いながら弁当を広げているのだが私の机の上には広げる弁当がなかった。皆が食べ始めても私はじっと机に座りながら窓の下の校庭を見ていた。教室が2階だったので広い校庭からその向こうの校門まで見えた。
真夏の太陽に校庭は照り返されてじりじりとやけているようであった。
校舎脇のポプラ並木の影が日差しが強いせいか、くっきりと校庭の砂の上にそのシルエットを描いていた。どこかで蝉がジージーと鳴いていた。
もう皆の食事が済む頃になってようやく母が小脇に何かを抱えながら校門を駆け抜けてくるのが見えた。広い校庭を必死になって私の教室のある校舎めがけて走って来る。その姿を2階の教室の窓から私はじっと見ていた。おそらく母はこの暑さの中を走り通しで汗びっしょりかいているのだろう。また何か着物でも質屋に入れてお金を作り私の弁当のお米を買っただろう。弁当の中は五分五分の麦飯でその中間には醤油をかけた鰹節が挟んであるのだろう。おかずはそれだけだろう。
校庭を斜めに駆ける母の後ろの影法師がなにか悲しい影絵のように思えた。その時つくづく貧乏はいやだ・・・と思った。
この一連の光景がその後もずっと私の頭から離れず、バイトをしながらの苦学生の時代も、仕事についてからの後の厳しい場面にもいつも思い出されたものである。
「あの時のせつなさ、辛さからみれば・・・」と何時も自分を奮い立たせてくれたのである。比較論的に物事を判断し、直面する問題をよりイージー(easy)に振り替えて処理できたのである。
このような底辺の辛さ(子供の頃にとっては)をおそらく我々の時代の誰もが経験しているものと思う。しかし世の中が豊かになり「豊饒の海」に育った現代の若者には幸か不幸か困難にぶち当った時にたどりつく座標の原点がなく、打たれ強さに希薄ながところあり、短絡的な行動に走ってしまう傾向があるのではないだろうか。
そんな母も他界して早12年。今月22日が命日だったので遅ればせながら墓参りに行ってこよう。
|
|
八束さんの<毎日が日曜日>を読んで
八束さんの上記記事を拝読させていただき大いに賛同いたしました。私の場合は氏ほど徹底しておりませんのでせいぜい「毎日が土曜日」くらいでしょうか…?
やはり定年近くなりますと誰でもその後の生活に思いを馳せるわけですが、それらに関する書物は本屋にたくさんあります。読んでいるうちにそこに書いてある「理想形」と現実の自分の置かれた環境が違うことに気づき焦燥感にあおられることがありましたが、決してあせることは無いと思います。
八束さんも言われておりますように、基本的に心身の健康さえ保たれておればあとは自分流のオリジナル・メニューで行けばいいのだと思います。
定年後2年目の私の現在の基本生活パターンは、下記のごとくになっております。
月曜日 10:00〜16:00 ボランティア (新宿) 17:45〜21:00 勤務(パート) (幕張)
火曜日 朝 〜 自由
15:30〜21:00 勤務(同上)
水曜日 朝 〜 自由
13:30〜18:30 勤務(同上)
木曜日 10:00〜16:00 ボランティア (新宿)
16:00〜 自由
金曜日 休日
土曜日 08:45〜13:30 勤務(同上)
15:00〜16:30 ボランティア(中国人に日本語指導)
日曜日 休日 ( 0800〜10:00 剣道練習 )
この生活パターンを決めたメリットは…以下の点です。
1.ボランテアでは大勢の人との交流がありますので勉強と刺激になります。
2.勤務は4〜5時間と短い時間でシフトを組んでおりますので疲れません。
3.昼間にかなり自由時間が取れますのでスポーツジムとか散歩を適宜入れることが出来ます。
4.千葉在住の外国人に日本語を教えること(千葉市国際交流協会の企画)により国際交流が出
来る。 5.周に一度ハードなスポーツ(剣道)で思いきり汗を流すことが出来る。
6.週2日の休日(金、日)はかならずKeepしている。
これからハッピ−・リタイアーをお迎えになります方々の何か参考になればとペンを取りました。
また、この度の43会総会で重要な職務を仰せつかりましたので上記の自由時間を存分にShareさせたいと考えています。(管理人注: 佐藤さんはこの度白門43会の副会長に就任されました。)
|
|
|
桜の季節 先日、御茶ノ水駅を電車で通過する際久々の景色なので子供のように身を乗り出して周りの風景を見ていた。 |
|
このHome Pageの管理人である三沢さんがかなり前にこの寧日雑感に自分の家の愛犬の事を書いた3人(3家族)を指して「愛犬同盟」と名づけた。3人ともこの上なく自分たちの家のワンちゃんをこよなく愛し、家族の一員として可愛いがっていた。 |
|
7月10日より9日間かけて3度目(3年越し)の北海道一周ツーリングに行って来ました。 |
|
|
安楽死 私の家には一匹の子犬が居る。 種類はポメラニアンという小型犬でもう我が家に飼われてから約14年にもなる。つまり問題無く老犬で人間年令に変えたらとうに80歳は過ぎているらしい。 14年前に未だ我が家の子供が幼かった頃千葉のそごうデパートのペット売り場で私が見つけて買ってきたのが始まりであった。 夏のものすごく暑い日にその子は小さな小さな檻の中にぐったりとなって惰眠をむさぶっていたが、私が近づく気配でスクッと立ち上がった。そして私を不安そうにまた何か懇願するような目つきで見つめていた。 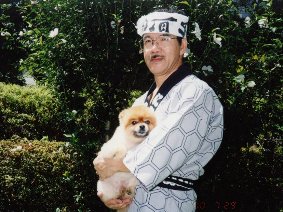 それが私と彼、レオ(彼の名前)との14年前の初対面であった。 それが私と彼、レオ(彼の名前)との14年前の初対面であった。まだ生まれたばかりのほんとにちいさな子犬で、店からはダンキンドーナツの箱の大きさのぐらいのBOXに入れて持ち帰った。家族はあまり犬を飼うことにのりきで無かったようだったが、子供の頃に犬を自宅で飼った経験のある私はどうしても犬を飼いたかった。しかし、それからの家族はいつのまにかこの子犬”レオ”を中心に全てが動くように変わっていってしまった。 子供達が帰宅しても先ず犬の姿が見えないと“あれっ? レオは?”から始まり“今日はレオの食欲が無いの?”とか、父親よりもまずレオの安否が先であった。犬年10歳位までは飛騨高山とか、八ヶ岳とか“ペットOK”のホテルを選んであちこち旅行もした。 まさしくよく言われる“家族の一員”に疑いも無くなって、その存在は大きいものに今はなってしまっている。 私には“主治医”などと贅沢なものは居ないがレオにはもう10年以上もかかり付けの獣医が近くに居る。過去には脱臼の手術、脱腸の手術、去勢等、入院も何回もしている。 最近、時々待合室でお会いする一人の老人が子犬を小脇に抱えて泣いていた。お話を聴くと医者からその子の病気が不治の病であり苦しみばかりなので“安楽死”を勧められたとのことであった。 それから数日あと、飲み会でお会いした会社の仲間に“お宅のワンちゃん元気?”と聞いたら5日前に亡くなったと目に涙をためて答えてくれた。17年も生きていろいろな病気(ガンも含む)を身体全体で引き受けて最近では昼も夜も苦しみに耐え抜く泣き声をもらしていた毎日であったらしい。何度かの医者の勧めの後、ご夫婦は“安楽死”にOKしたらしい。 最後はあれほど苦しんで悲鳴をあげ、眼を見開いていた愛犬はご主人の暖かい腕の中で医者の注射一本で安らかに死への旅についたとのことである。まるで“17年間ありがとう…”とでも言っているような死に顔でした、と彼は言っていた。  私の家のレオもいずれはその時を迎えねばならない。そのとき私は医者にその旨を告げられても決断が出来るであろうか? 私の家のレオもいずれはその時を迎えねばならない。そのとき私は医者にその旨を告げられても決断が出来るであろうか?犬は何も言わないだけに人間だけの判断でその生命の終息をきめて良いものであろうか? 人間ならば本人の意思確認も出来るし苦しみの度合いもわかる。しかし、犬の場合はそれは出来ない。 最近つくづく思うことは動物を飼うことはそれ自体楽しいし、沢山の癒しももらえる。だが、その長年の良いことの代償として上記のような“安楽死”の決断を迫られるとしたらそれはあまりにも冷酷な代償と言えるだろう。 出来るならば眠るように旅立ってもらいたい。 |