最近の活動
2024年11月6日(水)
第33回 中央大学 ホームカミングデーに参加して

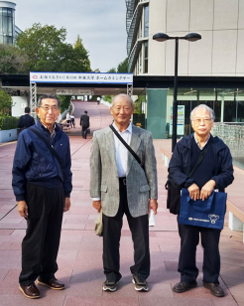
2024年10月27日(日)多摩キャンパスで開催された「ホームカミングデー」に行きました。久しぶりに朝早く浦和の自宅から武蔵野線で西国分寺経由立川に向かう。大学には8時30分頃到着。待ち合わせていた清家さん、森澤さん(写真)そして古賀さんと今日一日のイベントスケジュールなどが印刷された立派な冊子を片手に大学構内に向かいました。
1 式典は10時~12時、9号館(クレセントホール)で行われました。理事長、学長、その他の方々のご挨拶の概要は、以下の通りです。
○大村理事長
・中央大学は1885年創設され、その後幾星霜の時を経て139年が経った。現在は中長期計画も順調に推移している。
・この多摩キャンパスには今年4月「法と正義の資料館」や「大学資料館」を開設して、会員の皆様から好評を得ており、150周年に向けてさらに計画を推進して行く。
・今年の箱根駅伝は体調不良の選手が多く、まともに走れるのは二人だけだった。10月19日立川での予選会では、トップランク選手を温存しての参加だったが、6位で予選通過した。11月3日の全日本大学駅伝、来年の箱根駅伝では期待したい。
○河合学長
・パリオリンピックにOB/OG・学生あわせて16名、パラリンピックに学生1名が参加し、世界で活躍した。
・1885年英吉利法律学校として創設以来139年「実地応用の素を養う」という建学の精神のもと、有為な人材を輩出してきた。現在の中央大学は8学部、8研究科の大学院、2つの専門職大学院、あわせて3万人が在籍している。多摩55%、都心45%の比率になる。
・多摩キャンパスには近い将来スポーツ情報学部、情報農学部を新設予定。多摩において理系を含めた有為な人材を養成したい。新しい中長期計画を作成するので学員の皆様のご支援をお願いする。
 ○松田聖子さんからのメッセージ(大画面表示)
○松田聖子さんからのメッセージ(大画面表示)
・60歳を目前に控えて中央大学法学部・通信教育課程に挑戦することを決意し、無事に卒業できた。憧れていた中央大学で法律を学べたことは私にとって大きな喜びでした。
○小池東京都知事からのメッセージ(大画面表示)
・個人としてご縁のある中央大学の「ホームカミングデー」の開催をお祝い申しあげる。大学の益々のご発展を祈念いたします。
○親子三代表彰
・西田様、信田(しだ)様、福田様、岩崎様、田中・羽柴様、佐藤様、神谷様と7組の親子が表彰された。
・各組の皆様が母校愛に溢れた挨拶をしました。
○第2回学員栄誉賞授賞式
・飯塚翔太様:ロンドン・リオ・東京・パリ 4大会連続オリンピック出場、リオ400mリレー銀メダリスト。さすが世界で活躍するアスリートで、凛々しくスマートな青年でした。
・SEKAI NO OWARI Nakajin様:楽曲「Habit」が第64回日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞
○パリオリンピック・メダリスト 学員会会長賞特別賞授賞式 ・永野雄大(男子フルーレ団体金メダリスト)
・永野雄大(男子フルーレ団体金メダリスト)
・古俣 聖(男子オペ団体銀メダリスト)
・上野優佳(女子フルーレ団体銅メダリスト)
・江村美咲(女子サーブル団体銅メダリスト)(代理)
この後音楽研究会吹奏楽部の記念演奏を鑑賞して応援団の演舞で元気をもらい、次のイベント会場に向かいました。
2 中央大学ボクシング部後援会及びスポーツの未来(石井苗子会長との対談)
石井苗子氏(参議院議員)はTVキャスター、女優とマルチに活躍。中大との縁は元理工学部大橋教授と知己を得たことです。
ボクシング部との縁は石井氏が過去にマイク・タイソンの同時通訳を経験したことです。
同行した43会清家さんとは清家さんが警視庁築地警察署長の頃、道場で剣道の指導をしたそうです。石井さんは現在剣道3段です。石井さんは清家さんを「先生」と呼び握手を交わしていました。
3 日本を代表する水の研究者「山田正 機構教授」との対話型集会 玉川上水からの水を日本橋の川に入れることが出来れば水がきれいになる。などの提言を小池百合子東京都知事に提出、また国土交通省・東京都の意見交換会への参加など行政を巻き込んだ多面的な活動をされている。近年の水災害の特徴と防災についてのお話など、大変興味深いものでした。
玉川上水からの水を日本橋の川に入れることが出来れば水がきれいになる。などの提言を小池百合子東京都知事に提出、また国土交通省・東京都の意見交換会への参加など行政を巻き込んだ多面的な活動をされている。近年の水災害の特徴と防災についてのお話など、大変興味深いものでした。
43会の岡田孝子さん(中央大学理事)が集会の冒頭で挨拶されました。
4 この後中央大学の至宝「ベヒシュタイン製グランドピアノを楽しむ贅沢なプログラム」でオペラを楽しみました。福引抽選会には参加しないで、立川の居酒屋「玉河」で4人大いに盛り上がりました。中大の「ホームカミングデー」は今回参加人員が少なく、寂しい気がしました。
【矢崎 勝】
2024年7月9日(火)
第30回定時総会・講演会・懇親会の模様
(定時総会の模様) 白門43会の第30回定時総会・講演会・懇親会は2024年7月5日(金)、東京・上野の精養軒で開催されました。梅雨の真っ最中なのに東京地方は猛暑日の警報が出るほどの暑さでした。出席者はご来賓を含めて64名(うち女性7名)でした。今回の総会では清水会長が体調不良で欠席のため、清家春夫副会長が会長代行を務めました。定時総会の会場はこれまでと違う2階の藤の間で、横に長く、中に大きな柱が2本立っていて全体が見渡し難い部屋でした。
白門43会の第30回定時総会・講演会・懇親会は2024年7月5日(金)、東京・上野の精養軒で開催されました。梅雨の真っ最中なのに東京地方は猛暑日の警報が出るほどの暑さでした。出席者はご来賓を含めて64名(うち女性7名)でした。今回の総会では清水会長が体調不良で欠席のため、清家春夫副会長が会長代行を務めました。定時総会の会場はこれまでと違う2階の藤の間で、横に長く、中に大きな柱が2本立っていて全体が見渡し難い部屋でした。 会は小塚副会長の司会進行のもと、清家副会長が開会の挨拶ののち議長となって進められました。矢崎幹事長による2023年度事業報告、立岩会計幹事による2023年度収支決算報告と歌代監査による監査報告、続いて矢崎幹事長による2024年度の事業計画案、立岩会計幹事による2024年度予算案が提示され、いずれも異議なく承認されました。この中での特記事項は、来年2025年度は白門43会創立30周年となるので、そのためのプレイベントとして今年12月にはベートーベンの第九鑑賞会が開催され、来年5月には四国地方への記念旅行、7月には記念総会、その他記念誌の発行を行うことなどが紹介されました。またそのための寄付を募るのでよろしくとの話がありました。
会は小塚副会長の司会進行のもと、清家副会長が開会の挨拶ののち議長となって進められました。矢崎幹事長による2023年度事業報告、立岩会計幹事による2023年度収支決算報告と歌代監査による監査報告、続いて矢崎幹事長による2024年度の事業計画案、立岩会計幹事による2024年度予算案が提示され、いずれも異議なく承認されました。この中での特記事項は、来年2025年度は白門43会創立30周年となるので、そのためのプレイベントとして今年12月にはベートーベンの第九鑑賞会が開催され、来年5月には四国地方への記念旅行、7月には記念総会、その他記念誌の発行を行うことなどが紹介されました。またそのための寄付を募るのでよろしくとの話がありました。
続いて役員承認の案が提示されました、副幹事長に清水利夫幹事、森澤正瑞幹事、新たな幹事として澤畑寛治氏、玉澤宏氏、地方幹事として神林俊晄氏、合津五郎氏が提案され、承認されました。この後新任役員は演壇前に出て紹介されました。以上で議事は滞りなく取り運び、予定より早く終了しました。
(講演会の模様)
今回の講演の演題は「郷里鹿児島と幕末」で、講師は鹿児島県徳之島出身の正野建樹元会長でした。会場は同じ藤の間で行われました。以下、私が理解した概要を述べますが、拙い記憶を辿ってなので、正確を欠いているところもあるかもしれませんが、ご容赦願います。 お話は西郷隆盛が中心でしたが、西郷隆盛が生まれたのは鹿児島城下の下級武士の居住地となっている加治屋村でした。70世帯ほどの小さな村なのに、幕末から明治に掛けて活躍した大久保利通、東郷平八郎、大山巌、山本権兵衛などそうそうたる人物が輩出されました。薩摩藩主の島津斉彬公から見出された西郷はお庭番として身近に仕え、やがて篤姫を徳川13代将軍家定の正妻とすべく、奔走することになる。このとき公家の近衛家の養女にしてから嫁がせる計画だったが、その際に骨を折ってくれたのは月照という僧であった。後に安政の大獄で月照も西郷も狙われる身となり、故郷の薩摩に身を隠そうとするが斉彬公はすでに亡く、藩主は久光になっていたので二人を匿うどころか暗殺しようと企む。計画を知った二人は錦江湾で船から身を投げ、月照はそこで絶命、西郷は助けられて生き残り、復活の機会を狙う。
お話は西郷隆盛が中心でしたが、西郷隆盛が生まれたのは鹿児島城下の下級武士の居住地となっている加治屋村でした。70世帯ほどの小さな村なのに、幕末から明治に掛けて活躍した大久保利通、東郷平八郎、大山巌、山本権兵衛などそうそうたる人物が輩出されました。薩摩藩主の島津斉彬公から見出された西郷はお庭番として身近に仕え、やがて篤姫を徳川13代将軍家定の正妻とすべく、奔走することになる。このとき公家の近衛家の養女にしてから嫁がせる計画だったが、その際に骨を折ってくれたのは月照という僧であった。後に安政の大獄で月照も西郷も狙われる身となり、故郷の薩摩に身を隠そうとするが斉彬公はすでに亡く、藩主は久光になっていたので二人を匿うどころか暗殺しようと企む。計画を知った二人は錦江湾で船から身を投げ、月照はそこで絶命、西郷は助けられて生き残り、復活の機会を狙う。
やがて時代は移り、西郷は徳川攻めの総大将として江戸城総攻撃を行おうとするが、すでに将軍家定公は亡くなっているので、人情家の西郷は何としても総攻撃の前に、自分が送り込んだ篤姫を救出しようと試みる。しかし一方の篤姫は、自分は輿入れしたときから島津とは縁を切り、二度と戻らぬ覚悟でやってきた、今は徳川の人間だから徳川と運命を共にする覚悟であるとして、西郷の申し入れを拒否する。
江戸城無血開城ののち、戊辰戦争で奥州の各藩は新政府軍の攻撃を受け、敗れた会津藩などは過酷な処分を受けるが、領民から慕われていた庄内藩には寛大な処分が行われ、領地替えもなかった。それで庄内藩では南洲神社を建てて、その徳を偲んだという。
この後お話は、山本権兵衛の逸話に移ります。
後に総理大臣となる権兵衛は、海軍の将兵だったとき、品川の遊郭で、ときという遊女を見初める。妻にしたいと考えたが、彼は金を払って身請けするのではなく、強奪することを決心する。友人の手を借り、夜陰に紛れてボートを遊郭に横付けして強奪に成功する。その後遊郭側との話がついて妻に迎え入れることになるが、この時彼は妻に、今後何があっても離縁はしないことなどをしたためた誓約書を書く。妻に誓約書を書いて渡すなど当時は考えられないことだったが、彼はそれを実行し、生涯その約束を守ったという。あるとき妻が夫の乗船している船を見学に来て、船から桟橋に降りるとき、彼は彼女の履物を持って先に降り、桟橋で履物を揃えて待ったという。
(懇親会の模様)
懇親会は3階の桐の間で行われました、宴が始まる前に全員の集合写真を撮りました。

懇親会にはご来賓として、中央大学常任理事の塚原由紀夫様、中央大学学員会会長の久野修慈様、42年白門会幹事長の林直清様、白門44会支部長の吉永匡宏様、株式会社ノラ・コミュニケーションズの平方麗様をお迎えしました。
 懇親会は富田秀雄副会長の司会進行で進められました。最初に元応援部の小塚正人副会長のリードで「草のみどり」を斉唱しました。清家会長代行(上写真左)の挨拶に続いて、中大常任理事の塚原様(上写真中)と、学員会会長の久野様(上写真右)からご挨拶をいただきました。塚原理事からは中央大学の多摩キャンパスに新たに「スポーツ科学部」と「農業情報学部」が令和9年度を目標に新設されることになったことなどのお話がありました。久野会長からは若いころに南氷洋の捕鯨船や北方のサケ・マスの漁船に乗船したことなどの経験話の後、これからの少子化の時代に大学が生き残るために質の高い大学を目指して行きたいという抱負などが話されました。
懇親会は富田秀雄副会長の司会進行で進められました。最初に元応援部の小塚正人副会長のリードで「草のみどり」を斉唱しました。清家会長代行(上写真左)の挨拶に続いて、中大常任理事の塚原様(上写真中)と、学員会会長の久野様(上写真右)からご挨拶をいただきました。塚原理事からは中央大学の多摩キャンパスに新たに「スポーツ科学部」と「農業情報学部」が令和9年度を目標に新設されることになったことなどのお話がありました。久野会長からは若いころに南氷洋の捕鯨船や北方のサケ・マスの漁船に乗船したことなどの経験話の後、これからの少子化の時代に大学が生き残るために質の高い大学を目指して行きたいという抱負などが話されました。
 乾杯で宴が始められた後、遠方からの出席者と久しぶりの出席者6名の紹介があり、皆さんからひとことずつのご挨拶がありました。
乾杯で宴が始められた後、遠方からの出席者と久しぶりの出席者6名の紹介があり、皆さんからひとことずつのご挨拶がありました。
9つの丸いテーブルに次々に中華風の料理が提供されてしばらく歓談しましたが、皆さん久方ぶりの再会に話が弾んだようでした。
今回のアトラクションは、古賀忠夫さんの率いる「八重洲オッターバ」の皆さんでバイオリン、ビオラ、チェロ、ベース、ピアノなど8名の人たちで、ピアノの女性は美しい歌も披露してくれました。夜来香、エデンの東、高原列車は行く、思い出のサンフランシスコなどが演奏されました。

その後、有志による歌謡ショウがありました、出演は原田六生さん、富田秀雄さんと岡田孝子さん(デュエット)、玉澤宏さんで、皆さん自慢の喉を披露してくれました。

宴は最後に、副幹事長の星野則昭さんのリードで、全員が肩を組みながら「惜別の歌」を歌い、矢崎幹事長の閉会の辞で宴はお開きとなりました。

【三沢充男】
2024年1月22日(月)
「新春の集い」が開催されました
2024年1月19日(金)、白門43会の令和6年「新春の集い」が中央大学・駿河台キャンパス19階の「グッドビュー・ダイニング」で開催されました。これまでは上野池之端の東天紅上野店での開催でしたが、昨年4月に駿河台キャンパスがオープンしたため、久しぶりに母校キャンパス内のレストランでの開催となりました。
 広々とした西側全面と、南北の各半分ほどに明るい窓が開けていて、近隣の大学やビルなどが眼下に見通せる明るい会場でした。会場内は一つのテーブルに6人ぐらいずつ、下半身がすっぽり入るような座り心地よい椅子席やソファー席が配置されていました。また広々と見渡せる厨房ではスタッフが甲斐甲斐しく働いていました。
広々とした西側全面と、南北の各半分ほどに明るい窓が開けていて、近隣の大学やビルなどが眼下に見通せる明るい会場でした。会場内は一つのテーブルに6人ぐらいずつ、下半身がすっぽり入るような座り心地よい椅子席やソファー席が配置されていました。また広々と見渡せる厨房ではスタッフが甲斐甲斐しく働いていました。
この日の参加者は全部で55名(うち女性10名)で、このほかアトラクションの出演者が5名でした。開会前にまず全員で集合写真を撮りました(末尾に掲載)。 12時30分、星野副幹事長の開会の言葉と司会進行により会が始まりました。ここで校歌斉唱ですが、いつもなら小塚副会長のキビキビした振りのエールにリードされて歌うのですが、今年は元日に発生した能登半島地震のため七尾市出身の小塚さんが郷里へ戻られていて出席できなかったので、星野副幹事長の発声に合わせて全員で1番だけを歌いました。
12時30分、星野副幹事長の開会の言葉と司会進行により会が始まりました。ここで校歌斉唱ですが、いつもなら小塚副会長のキビキビした振りのエールにリードされて歌うのですが、今年は元日に発生した能登半島地震のため七尾市出身の小塚さんが郷里へ戻られていて出席できなかったので、星野副幹事長の発声に合わせて全員で1番だけを歌いました。
最初に清水会長の挨拶がありました。特筆すべきものとしては、来年2025年には白門43会の発足30年を迎えるので、四国地方への旅行その他いろいろの記念行事を行いたいとの話がありました。また43会には二人の画伯が居られて活躍されているとの話があり、町田譽曽彦さんと鹽野惠子さんが紹介されました。 町田さんは二科展には何十回も入選され、海外でも賞を受賞されたりしており、鹽野さんは頻繁に個展を開催されていて、お二人の一層のご活躍を期待したいとのことでした。町田さんは今回、富士山を描いたカレンダーや絵葉書をたくさん寄贈してくれました。
町田さんは二科展には何十回も入選され、海外でも賞を受賞されたりしており、鹽野さんは頻繁に個展を開催されていて、お二人の一層のご活躍を期待したいとのことでした。町田さんは今回、富士山を描いたカレンダーや絵葉書をたくさん寄贈してくれました。
この後久しぶりの参加者の紹介があり、続いて古賀幹事の乾杯の音頭で宴が始まりました。この日の料理はイタリアンで、厨房のスタッフが三人分くらいずつ皿に盛った料理を運んできてくれました。
しばらく歓談した後、いよいよ待望のアトラクションが始まりました。今回のアトラクションは、津軽三味線澤田流の「澤田美成会」の皆さんの演奏でした。艶やかな赤系統の衣装に黒い袴姿の女性4人と黒い衣装の男性1人(太鼓)の編成でした。
オープニングは黒田節で、三味線、笛、太鼓に合わせて槍を持った女性の演舞が行われました。黒田節は男性が踊るものとばかり思っていましたが、美しい女性が槍をしごいて踊る姿は妖艶さも加わり、間近で写真を撮っていた私は圧倒されてしまいました。
 津軽三味線は早い撥捌きが有名ですが、そればかりでもなく、優雅な演奏もされるようです。説明によると発祥は沖縄の蛇皮線で、それが長い歴史のなかで次第に本土を北上してきて津軽まで辿り着いたとのことでした。気候の悪い地域で遠くの人にも聞こえるように次第に大きな音で演奏されるようになったとの話もありました。
津軽三味線は早い撥捌きが有名ですが、そればかりでもなく、優雅な演奏もされるようです。説明によると発祥は沖縄の蛇皮線で、それが長い歴史のなかで次第に本土を北上してきて津軽まで辿り着いたとのことでした。気候の悪い地域で遠くの人にも聞こえるように次第に大きな音で演奏されるようになったとの話もありました。
平成26年には日本武道館で1124人の津軽三味線の大演奏会が行われ、ギネス世界記録に認定されたとのことでしたが、この日はそれとは対極的なソロでの演奏も披露されました。
この日は三味線担当の3人の人が担当を変ったりしながら演奏されましたが、極め付きの早い撥捌きの演奏がされる場面では会場から拍手が巻き起こり、一層ムードが盛り上がりました。また伝統的な曲ばかりではなく、会独自のオリジナルな曲の演奏も紹介されました。
30分の予定時間があっという間に済んでしまい、その後、途中から参加された元会長の正野さんと中央大学理事で学員会副会長でもある岡田孝子さんが挨拶されました。
司会進行の星野副幹事長のリードで惜別の歌の斉唱が行われました。プリントには4番までの歌詞が書いてあり、この歌は学徒出陣する学生を送り出すために中大先輩の藤江英輔先生が作曲されたもので、そのためには4番もぜひ歌って欲しいと私から星野さんにお願いし、快く承諾をしていただいたのですが、演奏のCDの方が3番までしかなく、残念ながら4番の歌唱は実現しませんでした。
最後に矢崎幹事長の締めの挨拶で宴は終了しました。
 なお、今回は歌代雄七さんがホームページへ連載している随想が100話に達したので、さきに50話までをまとめて出版した「森羅万象Ⅰ」に続いて、51話から100話までをまとめた「森羅万象Ⅱ」を発行し、「森羅万象Ⅰ」とともに実費頒布したところ、大勢の出席者に購入していただきました。
なお、今回は歌代雄七さんがホームページへ連載している随想が100話に達したので、さきに50話までをまとめて出版した「森羅万象Ⅰ」に続いて、51話から100話までをまとめた「森羅万象Ⅱ」を発行し、「森羅万象Ⅰ」とともに実費頒布したところ、大勢の出席者に購入していただきました。

【三沢充男】