変わるものと変わらないものと
「まむしに注意」という看板が人目を引いていた。
「東京の大学に進学するんだ!」と意気揚々と地方から出てきた学生が、「自分の田舎よりも辺鄙じゃないの。」と、東京でのは
ていたのはそにう遠いことではない。
1978年に全学移転して早24年。白亜の殿堂(という
よりも製薬会社の工場のようだともよく言われた。)
はいささかくたびれてはきたが、かぼそかった
桜の木々もようやくひとかかえもあるよう
な幹に成長し、桜広場は桜の森に
なりつつある。24年たってようやく
多摩校舎も大学らしくなってきた
と言ったら、いささか手前味噌
だろうか。
まむしの大学も2000年には
モノレールが開通し、まむしも
さぞ驚いたことだろう。
桜は大きくなったが、それ以上に
社会は激変しつつある。制度も物も
そして人も大きく動いてきた24年だった。 大学はそれに遅れまいと必死に追いかけてきた
というのが偽らざるところではないか。
昭和49年に卒業して29年目。こちらの方もいささかがたぴししてはきたが、まだまだ若い者には負けない(2000年前にも言われていたとか。)との心意気ではないだろうか。自分が学んだ駿河台校舎もいまはなく、多摩校舎は人ごとにしか思えない。なつかしさはなくとも、後輩たちが学ぶ多摩校舎を駿河台時代と比較して、その環境の良さをうらやましく思うこともある。
昭和45年4月の最初の授業の日、教室がわからずうろうろしたのは昨日のこと。歳をとると月日は飛び去るとはいえ、この内なるギャップはなんなのか。社会の変化に対応しなければ時代に取り残されるとはわかっていても、変わらないものに抱く憧憬はいかんともし難い。
多摩キャンパスにはお稲荷さんが祀られている。正式には金住(こんじん)稲荷と称されている。その昔、そのあたりが金住院という寺院の所有地であったところから名付けられたらしい。お稲荷さんが祀られている小山の参道には20本近い小さな赤い鳥居が立てられている。大学の中に取り残されてしまったお稲荷さんが、その移り変わりをどう思し召しているのかは知る由もないが、結構大切にされている(お賽銭箱には小銭が絶えることがない。)ところを見ると、少なくとも悪さはせずにこれからも大学の行く末を見守ってくれるようにお願いする他はない。
また、キャンパス内には本格的な茶室も建てられている。文学部出身の表千家千 宗左宗匠によって「虚白庵」と命名されたこの茶室は、1996年に文学部の茶道に詳しい教員の協力で作られたとか。教職員・学生が茶会を催す時に利用することができるほか、場合によっては卒業生が利用することも可能なようだ。茶室の空間で一服の茶に30年のほのかな苦みを感じるのも悪いものではない。
年々歳々花相似たり 歳々年々人同じからず。変わり行かざるを得ない人の世に、ほんのつかの間、花を夢見ることにしよう。
2002年8月 荒木 康裕(法学部政治学科)
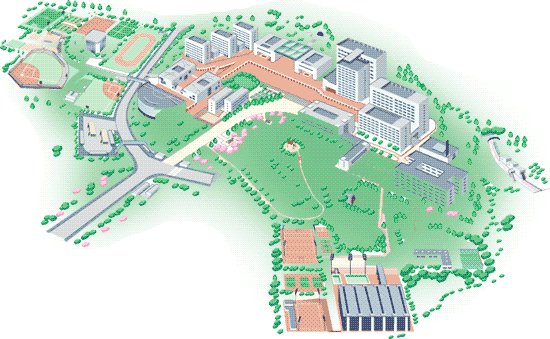
※マップをクリックすると
該当するサブページが開きます。